
方言
ばってん
方言の地域
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県
方言の意味
しかし、だけど
「ばってん」について
「ばってん」とは九州の肥筑方言における逆接を意味する接続詞で、「でも」「しかし」を意味する言葉です。この方言は九州の北西部を中心に使用されており、特に福岡県、熊本県、長崎県、佐賀県などで広く使われています。
言語学的な研究によると、「ばってん」は「そうであっても」を意味する「さればとて」や「もし~したとしても」を意味する「~ばとて」から発展したとされています。
英語の「but then」との関連は噂の域を出ておらず、確固たる証拠はありません。
九州では肥筑方言以外にも豊日方言や薩隅方言がありますが、「ばってん」という言葉は北西地区特有のもので、他の方言地区では使われていないことが特徴です。
また、東北地方の津軽弁では「ばって」という似た発音と意味の言葉が存在します。
これは、文化的な中心地からの距離によって方言が異なるという言語地理学の理論に基づくものと考えられています。
「ばってん」の使い方
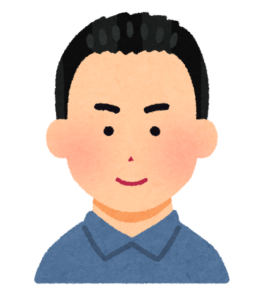
たく
今日はものすごい暑いね
ばってん、来週からは涼しくなるみたいよ

ひろし
「ばってん」の例文
- この料理は熱いばってん、美味い
- 週末の原宿は混むばってん行きたくない
- 昨日は雨だけど、ばってん今日は快晴だ


