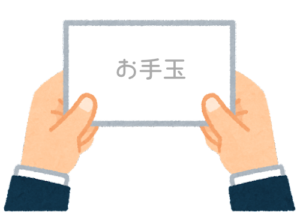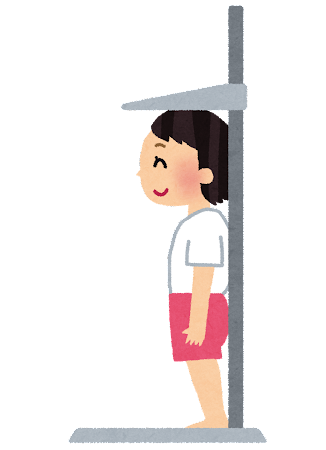
方言
たいこうさん
方言の地域
奈良県
方言の意味
とても背が低い人
「たいこうさん」について
大阪府では「たいこうさん」という言葉は「太閤さん」と読まれ、歴史上の人物である豊臣秀吉を指す意味で使われます。
対照的に、奈良県では同じ表記の「たいこうさん」が「とても背が低い人」という全く異なる意味で用いられています。
この方言の違いは、同じ言葉が地域によって異なる意味を持つことを示し、方言の地域特性を反映しています。
「たいこうさん」の使い方

みな
うちの兄ちゃん、たいこうさんやからバスケットボール苦手やねん
(うちの兄ちゃん、すごく背が低いからバスケットボールが苦手なんだ)
バスケットボールは背が大きい方が有利やからな

さつき
「たいこうさん」の例文
- うちのおとん、たいこうさんやからおかんより小さいねん
(私のお父さん、すごく背が低いからお母さんより小さいの) - あのおじさん、たいこうさんみたいで、目立つなあ
(あのおじさん、とても背が低いみたいで、目立つなあ) - たいこうさんやけど、運動は得意やねん
(背が低いけど、運動は得意なんだ)