
方言
はばかりながら
方言の地域
東京都
方言の意味
恐れ入りますが、恐縮ですが
「はばかりながら」の使い方
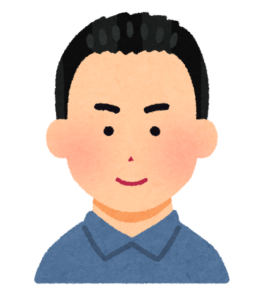
たく
此間の企画書すごい評判良かったよ
先輩…はばかりながら申し上げますが、此間の企画書は先輩と喧嘩して辞めた◯◯さんが企画したものです

みな
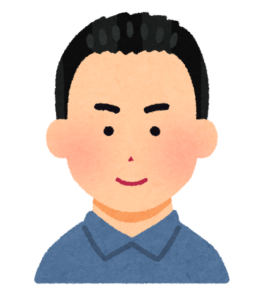
たく
なに…そうだったのか
「はばかりながら」の例文
- はばかりながらご要求には応じかねます
- はばかりながらその灰皿を取ってください
- はばかりながら何かの間違いではないでしょうか?

はばかりながら
東京都
恐れ入りますが、恐縮ですが
此間の企画書すごい評判良かったよ
先輩…はばかりながら申し上げますが、此間の企画書は先輩と喧嘩して辞めた◯◯さんが企画したものです
なに…そうだったのか