
方言
かまえる
方言の地域
高知県
方言の意味
準備する、支度する
「かまえる」について
高知県特有の方言「かまえる」は、「準備する」や「支度する」という意味を持ちます。
この言葉は、ただの準備を越えて、食事や酒席の準備など、来客のもてなしに関わる際に特に使われることが多いです。
高知県はお酒の消費量が多い地域として知られており、「かまえる」がお酒関連の準備に頻繁に使われることは、地域の文化や習慣を反映しています。
「かまえる」の使い方
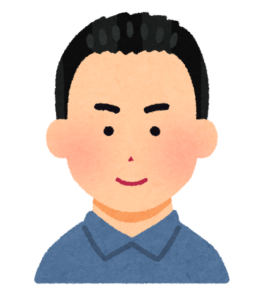
たく
今晩は宴会をやるの?
うん、もう全部かまえとったよ
(うん、もう全部準備してあるよ)

ひろし
「かまえる」の例文
- きょーお客さん来るから、部屋をかまえといて
(今日お客さんが来るから、部屋を準備しておいて) - 宴会のために料理をかまえるのに忙しい
(宴会のために料理を準備するのに忙しい) - お酒はもうかまえるから、遠慮なく飲んでね
(お酒はもう準備してあるから、遠慮なく飲んでね)


